くじらの不思議
クジラの研究者 中村玄先生にクジラについて教わる連載企画【クジラを学ぼう!】
中村先生は小さいころから動物や骨が大好きで、東京海洋大学に入りクジラの研究をスタート。大学4年生以降、北は北極海、南は南極海まで、世界各地でクジラを調査研究してきました。最終回である今回はそんな中村先生はいつクジラに出会い、どのような研究をしているのかをお話しいただきます。
クジラとの出会い
最初にクジラに出会ったのは、南米のアルゼンチンに1年間ホームステイをしていた高校生の時です。その際にアルゼンチンにあるバルデス半島がミナミセミクジラの繁殖海域だったので、ホエールウォッチングをすることになり、初めてクジラを生で見ました。


その時の印象は背中がつるっとしていて、幅が広く、泳ぐ速度はゆっくりだったことから、まるでカバが泳いでいるように思いました。
一緒に船に乗っていた他の国の留学生から「なぜ日本人はクジラを食べるのか」聞かれ、また別の留学生からは「日本は南極のサンクチュアリで違法に捕鯨をしている」と言われました。当時の自分はクジラが哺乳類であることを知っていた程度で、捕鯨の歴史や資源管理について考えたことはありませんでした。そのため、大学でクジラについて勉強するのも良いかもしれないと、一瞬と思いました。
帰国した翌年、東京水産大学(後の東京海洋大学)へ進学しましたが、当時はクジラの授業や研究室はありませんでした。もともと生き物が全般的に好きだったので、魚類や無脊椎動物、藻類などの生き物の研究室を目指していました。ところが、研究室配属をする3年次に加藤先生(※)が大学に赴任され、クジラの研究室ができたのです。それまでクジラについて勉強することは全く無かったのですが、私たちと同じ哺乳類であるにも関わらず、海の中でしか生きられないクジラに親近感や興味が湧き、鯨類学研究室に入りました。
※加藤先生・・・加藤秀弘(一財)日本鯨類研究所顧問、東京海洋大学名誉教授
初めてクジラを触ったのはストランディング

研究室に配属されてすぐに茨城県の大洗にマッコウクジラがストランディング(座礁)しました、そこで初めて間近でクジラを観察する機会を得たのですが、その印象は「デカくて臭い」でした。死後3~4日経っており、哺乳類の死体特有の不快さと、力一杯押してもびくともしない巨体に圧倒されました。

ちなみにこの個体は今でも大洗水族館に骨格標本として展示されています。骨格標本を作る過程で、骨格の調査や計測をしたり、水族館に展示される際に補助として立ち会わせてもらったりと、色々と思い入れの多い個体です。
その後、卒業論文の研究テーマとして「沖縄に来遊するザトウクジラの個体数の推定」が与えられ、実際の調査の様子を知るために沖縄に行きました。美ら海水族館が20年近く取りためたデータを見せていただいたり、間近で生きたクジラを見ることができました。

調査船のエンジンを切って漂っていた時、急に船のわきからクジラが顔を出しました。とっさにカメラを構えましたが、大きすぎてフレームに収まりきりません。体表にはおびただしい数のフジツボが付いています。クジラの頭は音を立てずにどんどん高くなっていきます。高さはゆうに3mくらいあるでしょう。水面からザトウクジラの大きな目玉がのぞき、ギョロリとこちらを向いたあと、その巨大な頭は再び静かに海に沈んでいきました。
きっとザトウクジラも我々に興味を持って観察していたのでしょう。好奇心旺盛で色々なことを考えている巨大な動物を目の当たりにし、あらためてクジラって面白いなと思いました。
世界各地でクジラの調査


クジラの調査のため、北は北極海、南は南極海と世界各地に行きました。極域は冬になると氷が張り、極夜のため1日中真っ暗です。そのため洋上調査は夏におこなわれます。2006年から2007年にかけて参加した第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPA II)は11月に出発し3に日本に戻ってくるという約5ヶ月にもわたる長い調査でした。初めて訪れた南極海では、深い青色をした巨大な氷山や紅蓮の炎のような夕焼けなど、陸での生活ではまず見ることのない雄大な自然を目の当たりにしました。一方で、グリーンピースやシーシェパードなどの反捕鯨団体による妨害も受けました。船による体当たりをされたり、薬品瓶や発煙筒を船に投げ込まれたりするなど、危険な妨害行為を受け、背筋が凍る思いがしました。

クジラの骨格標本は非常に大きいため、博物館で収蔵されているクジラの標本数は他の動物に比べると極めて少ないです。私が専門としている骨格形態に基づく分類研究には、産地ごとにできるだけ多くの骨格標本が必要です。そのためアメリカ、南米、ノルウェーなど各国の博物館に行き、バックヤードに保管されている骨をひたすら計測しました。この写真はコククジラですが、頭の大きさだけでも私の身長よりはるかに大きいです。

こちらは南米の最南端、ティエラ・デル・フエゴ島にあるクジラの研究施設です。建物の前にはクジラの骨が置かれています。マゼラン海峡を間近に望むこの場所は、日本から最短で約30時間かかります。研究所に着くまでの道はほとんど舗装されておらず、本当にこんなところに人が住んでいるのか疑問に思いました。ところが、クジラの骨格研究者の中では有名な研究施設で、芳名帳には日本人を含む世界各国の著名な研究者の名前が多く書いてありました。この施設にしか保存されていないクジラの標本もあり、場所の辺鄙さとは裏腹に、とても豊かな標本を有する研究施設でした。

この写真(上)は中東のクウェートです。ある日、クウェートの行政の方からファイラカ島(ペルシャ湾)に大型のクジラが漂着したので、骨格標本を作りたいので技術的なアドバイスが欲しいと研究室に連絡がありました。加藤先生や標本製作会社の方とともに現地に入り、骨の調査や骨格標本を作るための準備作業をしました。この島はかつて湾岸戦争でイラク軍に占拠され、その後、多国籍軍によって奪還されました。そのため場所によっては地雷が残っているかもしれないからあまり一人でウロウロするなと言われ、ドキドキしながら骨の処理をしたことを覚えています。まさか自分が中東に行くとは思っていなかったので、クジラが取り持ってくれた縁とも言えます。

2007年から2018年にかけての10年以上、網走、釧路、八戸、石巻など日本の沿岸域でおこなわれていた鯨類捕獲調査に毎年のように調査員として参加しました。ミンククジラを対象に年間120頭程度が捕獲され、その科学的な調査を日本鯨類研究所や国際水産資源研究所の職員さんを中心に、研究室の学生調査員ら4~5人と泊まり込みで調査していました。
この時にサンプリングしたり調査したミンククジラが自分のクジラ研究の礎になっています。
最近取り組んでいる研究内容について

最近興味を持って取り組んでいるテーマとしてヒゲクジラはどうやって鳴いているのか、というものがあります。
クジラの仲間の場合は、「クジラの体について」でも解説しましたが、多くの哺乳類が持つような声帯がありません。ハクジラ類の鳴き方は1970年~80年代に解明されています。鼻道に音を出す小さな袋があり、そこに空気を出し入れすることで音をだしますのです。
ところが、ヒゲクジラ類についてはごく近年まで、音を出すメカニズムが解明されていませんでした。ヒゲクジラ類にはハクジラ類のような鼻道の構造物がありません。代わりにハクジラとは違い喉に喉頭嚢(コウトウノウ)と呼ばれる袋を持っています。私は鯨類捕獲調査の現場でこの袋を調べた時、オスとメスで形が違う事がわかりました。一般的にヒゲクジラの多く、特にザトウクジラは繁殖期にオスがよく鳴くことが知られています。そのためオスの方の袋が著しく発達している理由として、このようなヒゲクジラ類の生態が関わっているだろうと考え、論文を書いています。また、ミンククジラ以外の種の喉頭嚢の形態がどのようになっているのかについて学生が研究しています。

また、クジラヒゲの隙間からしか見つかっていないカイアシ類についても興味を持っています。この種は1879年に北極海で初めて記載され、その後南半球やインド洋からも報告されていますが、研究事例が非常に少なく、彼らがどういう生活史を送っているのかわかっていません。クジラヒゲの隙間という非常にニッチな場所を生活の場として選んだ生物が、どのようにクジラと共に進化してきたのか、非常に興味深いです。

調査ではストランディング(座礁)したクジラを研究することもよくあります。日本でもたびたび話題になりますが、ストランディングする理由については明瞭な答えはなく、様々な説があります。
クジラは海を回遊しますが、その際に指標の一つとして地磁気を使っていると考えられています。地磁気と等高線が交差する遠浅の海岸で座礁が多いことが報告されることから、地磁気と海底の環境が要因となる場合もあります。また、寿命、病気、人工物を食べてしまったなどの理由から個体が弱り、風や潮の影響で岸近くに来てしまい打ちあがってしまうこともあります。他にも、個体数調整説。小型鯨類などでは個体群調整を目的とした自殺をしているという説もあります。
ひとつ言えるのは大地震の予兆との関係はないこと、そして、人間の影響が全てではないことです。
ストランディングは人間の文明が発達する前から世界各地で起きている事象で、様々な理由で引き起こされているのです。
クジラという生き物がいることを知らない人はほとんどいないでしょう。しかし、私たちがクジラについて知っていることはごくわずかです。技術の進歩やちょっとした発想の転換などで、世界が驚く発見ができるかもしれません。ぜひ、これからの若い人たちにもクジラに興味をもってもらい、研究をすすめていって欲しいと思います。
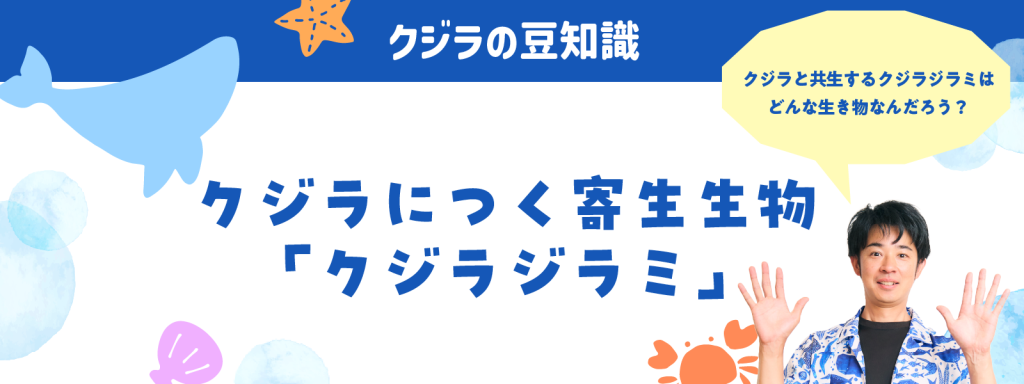
クジラの皮膚に白い斑紋がついた姿をみたことはないでしょうか。あの白い正体はフジツボやクジラの体に寄生した「クジラジラミ」と呼ばれる甲殻類の一種です。

見ているとゾワゾワしてしまうかもしれませんが、上で紹介したカイアシ類同様、クジラが居ないと生きていけない生き物です。
▶中村玄先生

中村 玄(なかむら げん)
1983年大阪生まれ埼玉育ち。東京水産大学(現:東京海洋大学)資源育成学科卒業
2012年東京海洋大学大学院 博士後期課程応用環境システム学専攻修了 博士(海洋科学)
(一財)日本鯨類研究所研究員を経て、現在は国立大学法人 東京海洋大学 学術研究院 海洋環境科学部門 鯨類学研究室 准教授。
専門は、鯨類の形態学。とくにナガスクジラ科鯨類の骨格。
著書「クジラの骨と僕らの未来」(理論社)(2022年青少年読書感想文全国コンクール高等学校の部 課題図書)「クジラ・イルカの疑問50」(成山堂)、「鳥羽山鯨類コレクション」(生物研究社)ほか
▶関連ページ
第1回「クジラってどんな生き物?」
第2回「クジラの種類」
第3回「クジラの生活について」
第4回「クジラの体について①」
第4回「クジラの体について②」
第5回「クジラの歴史について①」
第5回「クジラの歴史について②」
第6回「水産資源としてのくじら」
くじらについて
くじらの生態
くじらの不思議
